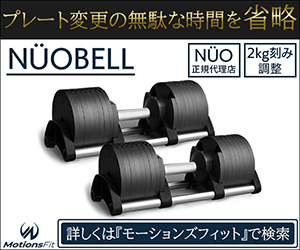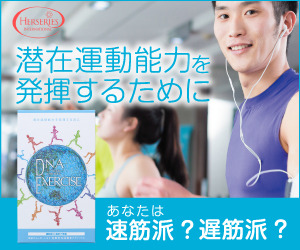背中の種目に『Tバーロー』があります。
実施別に以下の3パターンがあります。↓
立位マシン
出典:Gym Equipmentチャンネル T-Bar Row Machine Plate Loaded (L2)
チェストサポートマシン
出典:Steelflexfitnessチャンネル Steelflex Plate Load Series Instruction Video-PLTR(T-bar Row Machine)
バーベルシャフト
出典:uvacswimチャンネル T Bar Row
V型ハンドル使用
出典:Bodybuilding.comチャンネル Bent Over Two Arm Long Bar Row - Back Exercise - Bodybuilding.com
ハンドル未使用、直握り
上の動画のように、
ストリクトstyleで行うのも良いですが、
私個人的には、Tバーローといえば
チーティングstyleをおすすめしています。
その方が背中の発達に効果的だと感じるからです。
とても良い刺激が入ります。
(体力の消耗激しいし、キツイですが。。。)
チーティングstyleのTバーローを行う場合、
上で示した動画の内、どのパターンが良いのか?
それは、
バーベルシャフト+V型ハンドルのTバーローです。
立位マシンのTバーローは
踏ん張りやすくチーティングしやすいですが、
軸フレームが短いので、背に刺激が入る
最適なローイング軌道が得にくいです。
チェストサポートマシンのTバーローは
踏ん張りにくい姿勢なので
チーティングに不向きです。
これらの欠点が解消されているのが
バーベルシャフト+V型ハンドルのTバーローです。
本日は、チーティングstyleの
『 バーベルシャフト+V型ハンドルのTバーロー 』
の行い方や意識すべき点を
背中の厚みを得る場合、
広がりを得る場合にわけて
参考動画をもとに説明します。
ちなみに、
V型ハンドルとは、こんなやつです。↓
他ハンドルでもTバーローはできますが、
V型ハンドルで行う方が力発揮できます。
それと、
チーティングで高重量を扱うので
強い握力を必要とします。
背部を鍛える事を目的に行うので
迷わずリフティング用ストラップを使用し
握力の負担を低減させて下さい。
スポンサードリンク
背中の厚みを得る場合
ターゲットの筋肉
ここで言う、
背中の厚みとは上背部筋群の発達
のことです。上背部筋群を示します。
(刺激すべき筋肉を把握する事は基礎中の基礎です。)
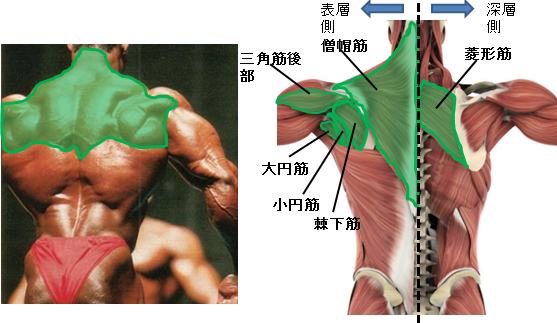
特に僧帽筋への刺激を重視しています。
僧帽筋、菱形筋、三角筋後部、大円筋、小円筋は、
今回のTバーローの挙げ下ろしの両動作時で働き、
棘下筋は下ろし動作時で強く働きます。
(肩関節の安定確保)
行い方
参考動画です。↓
0:45以降
元ミスターオリンピアのロニー・コールマンさんです。
この映像は、DVD『The Unbelievable』のものです。
(使用重量がヤバイです(笑)。迫力満点のトレDVDです。)
昔、これを購入し初めて観た時は、
その迫力に圧倒されましたが、
次第に『雑な感』や『反動の多用』に
疑問を抱くようになりました。
当時は狭い了見で観ていたので、
そう感じてしまったのは仕方ないですが、
今ではわかります。
これは筋肥大を促すとても良い行い方です。
私が思う、ロニーさんのTバーローの要は
バーベルを下ろす動作です。
全身の連動や反動で爆発的に引き挙げた
バーベル重量を
(ストリクト反復では扱えない程の重量)
落下させるように下ろし、
(「勢い=重力による加速」を完全に殺さず下ろす)
それをボトム位置でしっかり上背部が受け止める、
これを繰り返し強烈な刺激を入れています。
このように、上背部を狙ったチーティングstyleの
バーベルシャフト+V型ハンドルTバーロー は、
チーティングで高重量を扱い、
ブレーキとして上背部筋群を働かせて
勢いがついて下りるバーベル重量を受け止める、
(勢いがついた重量は、その重量より大きい負荷になる)
これを意識して行って、
筋損傷しうる強烈な伸張刺激を
上背部筋群に入れて筋肥大を促します。
腰が丸まらない範囲で肩甲骨を少し広げて
受け止める事ができるとなお良いです。
(高負荷の受け止めなので、意識せずともそうなりますが)
但し、受け止めの際、
ボトム位で一気に受け止める(=急ブレーキ)
ように行わないで下さい。
危険ですし、
東京大学 石井教授著『石井直方の筋肉の科学』
によりますと、急ブレーキをかけるような
過激なエキセントリック刺激を繰り返す事は
mTORのリン酸化を下げ、
タンパク質の分解を進めてしまい、
筋肥大にマイナスになる可能性があるようです。
(マウス実験による結果)
なので、うまく表現できませんが、
ロニーさんの動画の様に
なめらかなブレーキングでボトム位で止まる
といった感じで行うと良いです。
重要なのは下ろす動作と書きましたが、
引き挙げ動作を疎かにするわけではありません。
引き挙げ時は、爆発的動作を意識して行います。
これによって、多くの速筋線維が動員されます。
また、引き挙げ時の
レッグドライブや上体のあおり、肘の引きだけでなく
肩甲骨の寄せ(内転)も意識しましょう。
これにより、重視している
僧帽筋をより働かせる事ができます。
全動作とおして、
腰が丸まらない様に気を付けて下さい。
背中の広がりを得る場合
ターゲットの筋肉
背中の広がりを得る
=広背筋・大円筋・小円筋の発達
ということです。
広背筋、大円筋、小円筋を示します。
(刺激すべき筋肉を把握する事は基礎中の基礎です。)
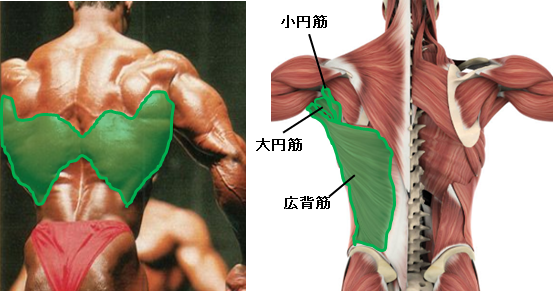
広背筋、大円筋、小円筋は、
今回のTバーローの挙げ下ろしの両動作時で働きます。
行い方
Tバーローはバーの片端を支点にした
円軌道のローイングになるので、
通常のローイング種目よりも
斜め後方に負荷がかかります。
なので、Tバーローは、
広背筋を刺激するのに良い軌道
(=肩関節の伸展方向)
が得られます。
ですが、広背筋をしっかり刺激するには
短縮側も伸展側も可動域が狭いです。
広背筋を
ギュッと強く縮み固まるほど短縮できないし、
強く引き伸ばされるほど伸張もできません。
個人的に、Tバーローは
広背筋を鍛える種目として
中途半端な感が否めないんです。
そこで、割り切って、
広背筋を狙ったTバーロでも下ろす動作を重視し、
ブレーキとして広背筋、大円筋、小円筋を
働かせる事で強い伸張刺激を入れていきます。
参考動画です。↓
出典:Diesel Joshチャンネル T bar Rows
体の連動や反動で爆発的に引き挙げた
高重量のバーベル負荷を
落下させるように下ろし、
(「勢い=重力による加速」を完全に殺さず下ろす)
それをボトム位置でしっかり
広背筋、大円筋、小円筋が受け止める、
これを繰り返し強い伸張刺激を入れています。
このように、
広い背中づくりを狙ったチーティングstyleの
バーベルシャフト+V型ハンドルTバーローでも、
チーティングで高重量を扱い、
ブレーキとして広背筋、大円筋、小円筋を働かせて
勢いがついて下りるバーベル重量を受け止める、
(勢いがついた重量は、その重量より大きい負荷になる)
これを意識して行って、
筋損傷しうる強烈な伸張刺激を
広背筋、大円筋、小円筋 に入れて
筋肥大を促します。
但し、こちらも
急ブレーキで受け止めるような事はせず、
動画のように、なめらかなブレーキングで
ボトム位で止まるといった感じで行うと良いです。
下ろし動作にはもう1つポイントがあります。
腰が丸まらない範囲で
腕とお尻を離しながら下ろす事です。
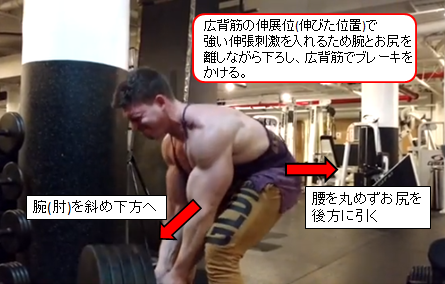
出典:Diesel Joshチャンネル T bar Rows
こうする事で、
広背筋が比較的伸展した位置で
強い伸張刺激を入れる事ができます。
そして引き挙げる際は、
広背筋の短縮を促すために、
肘を後方へ引く(肩関節の伸展) ことと
腰の前方突き出しを強調する事で
腕とお尻を近づけながら引き挙げます。
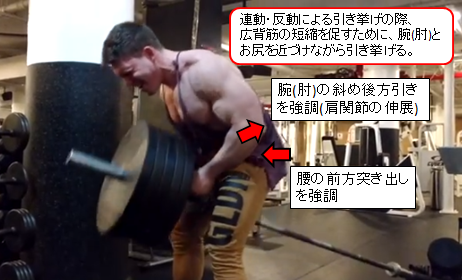
出典:Diesel Joshチャンネル T bar Rows
全動作とおして、
腰が丸まらない様に気を付けて下さい。
今回紹介しましたTバーローは、
けっこう難しく、怪我のリスクもあります。
なので、
初心者やトレ経験が浅い方にはおすすめ致しません。
中・上級者の方が行う場合でも
最初は高重量で行わず余力ある重量から開始し、
動作に慣れてから高重量を扱って下さい。
やり込む事で、
背中のレベルを1、2段引き上げてくれます!

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから
札幌パーソナルトレーニングZeal-K
札幌パーソナルトレーニングZeal-K
facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/
スポンサードリンク