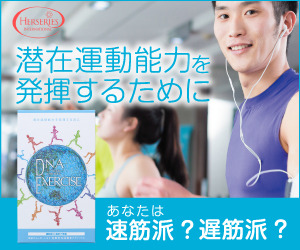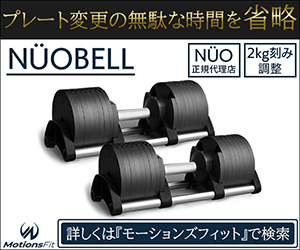昔、腰部や脊柱起立筋だけでなく、
背中の厚み(上背部筋群の発達)を得ようと
デッドリフトをやり込んだ時期がありました。
高重量を引っこ抜ければ、
自然と背中の厚みが得られると思い
取り組んでいました。
その結果、
扱う重量はかなり伸び、背中も発達しましたが、
その発達の程度は、期待外れでした。
デッドリフトは、その名のとおり辛いです。
視界に流れ星みたいなものが現れたり、
一瞬、立ちくらみの様に
意識がとびそうになる事もありますね。(笑)
なのに発達具合がいまいちでした。。。
そもそも、
背トレにデッドリフトを採用した理由は、
『Big3種目だから 』、
『○○選手がやってるから』
といった非常に短絡的なものでした。
今ふり返ると、
背中にバーベル負荷を乗せて行う事を
理解していなかったので、
いまいちな成果というのは当たり前です。
本日は、
背中の厚み(上背部筋群の発達)を得るために行う
『スナッチグリップ・デッドリフト 』の
行い方や意識すべき点を説明します。
スポンサードリンク
上背部とはどこの部分?
ここで言う『上背部』
=今回の種目で刺激する筋肉
とはどの部分かを先に示しておきます。
下の緑部です。↓
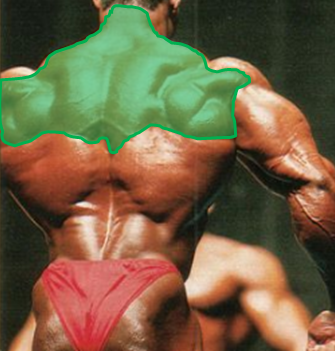
具体的に筋肉名で言いますと、
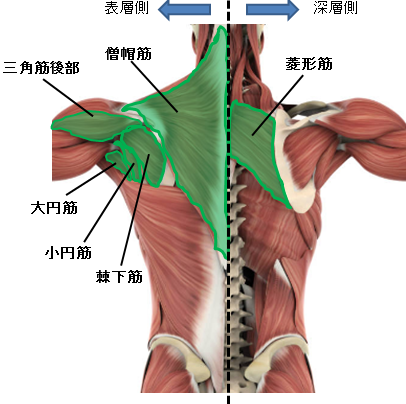
僧帽筋(そうぼうきん)
棘下筋(きょくかきん)
小円筋 (しょうえんきん)
大円筋(だいえんきん)
三角筋後部(さんかくきんこうぶ)
菱形筋(りょうけいきん) など
となります。
このうち、今回のデッドリフトでは
僧帽筋への刺激を特に重視しています。
デッドリフトと上背部の関わり
上背部の筋肉が
力を発揮しながら伸び縮みする事で
デッドリフトの動きになるわけではありません。
上背部の筋群は
デッドリフトの主動筋ではないという事です。
ですが、デッドリフト中の
上背部筋群の役割を考えると、
筋肥大しうる良い刺激になる事がわかります。
その役割とは、
肩甲骨のアライメント(肩甲胸郭関節)と
肩関節(肩甲上腕関節)の
安定を保つ事です。
僧帽筋や菱形筋などが力発揮しているので
バーベルに引っ張られて
肩甲骨が剥がれたりすることが無いし、
三角筋後部、棘下筋、大円/小円筋などが
力発揮しているからバーベルに引っ張られて
肩が抜けたりすることが無いわけです。
このように、
上背部の筋肉はデッドリフト中に
強く引っ張られ、それに抗って耐えています。
(=等尺性収縮:アイソメトリック収縮)
なので、
デッドリフト動作中の上背部には、
強い張力・緊張(メカニカルテンション)が発生し
多くの筋線維が動員されます。
また、引きの初動では
ブレーキ筋として働く側面もあるので
筋損傷しうる強い伸張刺激も得ることができます。
(=伸張性収縮:エキセントリック収縮)
さらに、上述のとおりデッドリフト中の上背部は
アイソメトリック収縮(等尺性収縮)と
エキセントリック収縮(伸張性収縮)が主で、
コンセントリック収縮(短縮性収縮)は
ほぼ無い(あってもその可動域は狭い)ので
ベントローなどの使用重量より高重量が扱えます。
纏めますと、
デッドリフトは高重量のバーベルを使って
上背部にとても強い張力・緊張と
筋損傷しうる伸張刺激を与える事ができる種目
という事です。
これらの刺激は筋肥大反応を促してくれます。
今回紹介するデッドリフトを行う際に
ただ漠然と引き上げ、下ろすのではなく、
上記の上背部の関わり・役割を意識して、
バーベル負荷をズシリと背中に乗せながら行う事で、
腰部・脊柱起立筋だけでなく
上背部筋群の発達も得られ
背中の厚みを獲得する事ができます。
ダンベル・外旋リバースYレイズ⇒スナッチグリップ・デッドリフト
今回紹介するデッドリフトは、
『スナッチグリップ・デッドリフト』です。
このデッドリフトで上背部の筋群を
より動員・刺激するために
アクチベーション種目
『ダンベル・外旋リバースYレイズ』
↓
メイン種目
『スナッチグリップ・デッドリフト』
の順で連続で行います。これで1セットになります。

アクチベーション種目
ダンベル・外旋リバースYレイズ

メイン種目の直前にこの種目を行う目的は、
メイン種目で上背部の筋活動を
増加させるためです。
注意点は、
軽負荷で行い、
限界まで反復しない、決して追い込まない事です。
実際、Júniorさん達の研究 で
軽重量、限界まで行わない事前種目の実施が
メイン種目の筋活動を増加させる事が
確認されています。
(疲労するまで行った場合、メイン種目の筋活動は低下する事がAugustssonさん達の研究で示されています。)
メイン種目
スナッチグリップ・デッドリフト

出典:bruno082985チャンネル Snatch Grip Rack Pulls
このデッドリフトは
他のデッドリフトと比較して
肩甲骨を安定させる肩甲帯の筋群を特に強化できるので、
上背部を刺激するデッドリフトに適しています。
なので、スナッチグリップ・デッドリフトは
上背部の筋群に非常に強い張力・緊張と
筋損傷しうる伸張刺激を
与える事ができます。
このデッドリフトの開始位置は、
腰・背の丸まり防止、
高重量の使用を狙うために
床からバーベルを引くのでは無く、
スネの中間位あたりから引けるように
パワーラック等でバーベルの高さを調整します。
上背部にバーベル負荷がしっかり乗るのであれば
膝下あたりから引けるように調整しても構いません。
そして、このデッドリフト中の肩甲骨は、
努めて肩甲骨を寄せる事はせず、
バーベルを引き上げた直立位以外、
腰・背中が丸まらない範囲で
あえて肩甲骨を広げて行います。
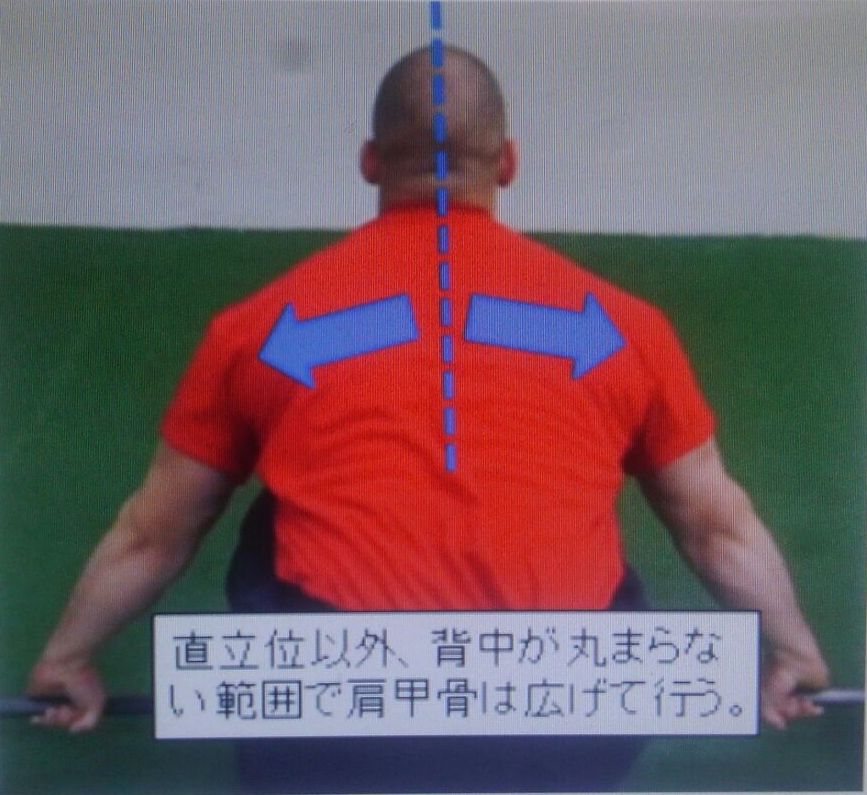
出典:FitWorldExposedチャンネル How To Snatch Grip Deadlift For A Thick & Wide Back
こうする事で、
僧帽筋や菱形筋などが伸びた位置で
強いテンションをかける事ができます。
このように、筋肉が伸びた位置で
強いテンションがかかると、
(=筋肉伸展位で強いアイソメトリック収縮)
mTORシグナル伝達経路が活性化したり、
(体に備わる筋肥大の仕組み)
筋肥大の成長因子
『IGF-1(インスリン様成長因子)』の
(自己)分泌が促進されます。
また、
引きの初動でブレーキ筋として働く時は
筋損傷が得やすくなると考えられます。
それと、
このデッドリフトはグリップ幅が広いので
通常のデッドリフトより
強い握力を必要とします。
上背部を鍛える事を目的に行うので
迷わずリフティング用ストラップを使用し
握力の負担を低減させて下さい。
ダンベル・外旋リバースYレイズの行い方
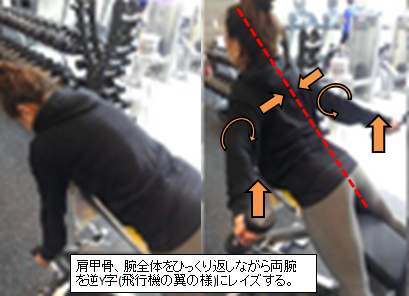
ベンチを30°程度インクラインに設定し、両腕を垂らし、両手の平を向かい合わせてうつ伏せになる。
肩甲骨の寄せと両腕の外回しを行ないながら、両腕を逆Y字に挙げる。
挙げたポジションで2秒程度保持して元に戻す。保持中は上背部筋群(僧帽筋、三角筋後部など)のギュッとした収縮を感じとる。
軽負荷で上背部筋群が熱くなる(パンプ感)まで反復するが、疲労困憊までは反復しない。
スナッチグリップ・デッドリフトの行い方
参考動画です。↓
出典:bruno082985チャンネル Snatch Grip Rack Pulls
実施時のポイントは以下です。
セッティング・グリップ幅
パワーラック等で開始位置(=バーベル位置)をスネ中間位又は膝下に設定する。
グリップ幅の目安は、片方の腕を横に伸ばし、その腕の握りこぶしから反対側の肩までの距離(PiperさんとWallerさんのレビュー論文)。可能ならそれより広くてもよい。
引き
引き始めの肩甲骨は腰・背中が丸まらない範囲で広げて、バーベルが浮かない程度にまずは引き、上背部筋群にグッとテンションをかける。(引き始めに上背部に負荷を乗せとく)
上背部筋群にテンションがかかったら、広げた肩甲骨を維持したまま力強くバーベルを引き上げる。(上背部筋群の緊張を意識する)
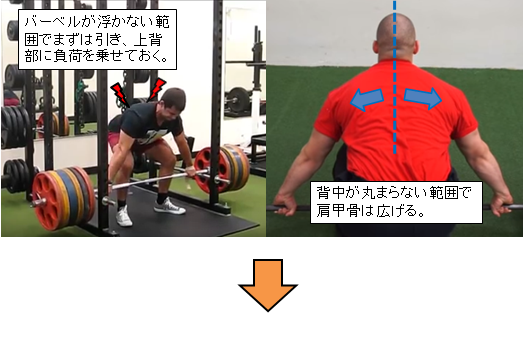

出典:FitWorldExposedチャンネル How To Snatch Grip Deadlift For A Thick & Wide Back
バーベルが静止から上がり始めた瞬間、肩甲骨や肩関節が引き剥がれない様に上背部筋群がブレーキ筋として働くので、筋損傷しうる伸張刺激が得られます。以後、上背部はアイソメトリック収縮でバーベル負荷の引っ張りに抗う(強い緊張が維持される)。
直立ポジション
引ききった直立位置では僧帽筋中・下部などのテンションが抜けるので、肩甲骨を少し寄せて収縮させる。

出典:bruno082985チャンネル Snatch Grip Rack Pulls
出典:FitWorldExposedチャンネル How To Snatch Grip Deadlift For A Thick & Wide Back
下ろす
下ろす際は腰・背中が丸まらないよう気を付けながら、肩甲骨を広げて上背部筋群にバーベル負荷をのせながら下ろす。(上背部筋群の緊張を意識する)
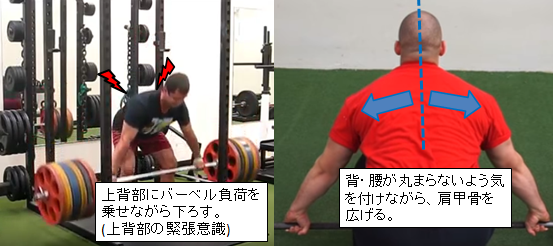
出典:bruno082985チャンネル Snatch Grip Rack Pulls
出典:FitWorldExposedチャンネル How To Snatch Grip Deadlift For A Thick & Wide Back
1回1回、ラックにバーベルを置き、
開始姿勢や引き始めのテンションを
入れなおして反復します。
けっこう難しく、怪我のリスクもある
デッドリフトなので、最初は高重量で行わず
余力ある重量から開始して下さい。
動作に慣れ、しっかり上背部に
負荷を乗せるスキルが身についた状態で
高重量が扱えるようになれば、
厚く逞しい背中が得られると思います!

パーソナルトレーニングのお問い合わせはこちらから
札幌パーソナルトレーニングZeal-K
札幌パーソナルトレーニングZeal-K
facebook https://www.facebook.com/ZealKenta/
スポンサードリンク